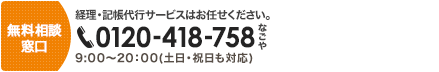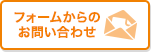こんにちは。突然の雨に驚いたり、暑さに負けて冷たいものばかり口にしてしまう季節ですね。体調を崩しやすい時期でもありますので、くれぐれもご自愛ください。
さて、今回は「経費精算システムを導入しても“紙”が減らない理由」についてお話しします。
ペーパーレス化の一環として多くの企業が経費精算システムを導入していますが、
「結局、紙の書類がなくならない」
「まだハンコ文化が残っていて、あまり効率化されていない」
という声をよく耳にします。
この記事では、「なぜシステムを入れても紙文化がなくならないのか?」という現場のリアルを深掘りし、経理担当者の視点から改善のヒントをお届けします。読み終えたあと、身近な業務に思い当たる場面がきっとあるはずです。
目 次
-
1.なぜ“紙”が減らないのか?よくある理由5つ
-
2.「紙が減らない」問題に対処する3つのステップ
-
3.まとめ
1.なぜ“紙”が減らないのか?よくある理由5つ
①. 原本提出を求める運用ルールが残っている
たとえば、「電子データでも申請はできるけれど、最終的には原本を経理に提出してもらいます」という運用。
このルールは、過去の税務調査対応や、内部統制の厳格化により「紙の証憑(しょうひょう)を保管するのが当たり前」とされてきたことに由来します。
また、「紙で残しておいたほうが安心」といった心理的な要素も絡んでいる場合が多く、制度と慣習の間にある“空白”が原因になっていることも。
②.印鑑文化が根強く残っている
「システムで申請しても、最後は印刷して上長のハンコが必要」というケースも未だ健在です。
こうした文化は、特に年次の高い社員が多い企業や、長く紙ベースで業務を続けてきた部署で根強く残っています。
電子承認フローへの移行には、稟議ルートの見直しや合意形成が必要になるため、経理主導での導入には限界があるという声もよく聞かれます。
③. システム運用と現場運用が分断している
部門ごとにシステムの使い方や運用スタイルがバラバラだと、「結局紙の方が早い」といった判断がなされてしまうことがあります。
たとえば、営業部門では「移動中にスマホで入力できれば十分」というニーズがある一方、
経理では「原本がないと内容確認や証憑チェックが不安」と考えている場合など。
このような“温度差”があると、紙とデジタルの併用状態が常態化してしまい、せっかくのシステムが生かされません。
④.電子帳簿保存法への理解不足
2022年の電子帳簿保存法改正で要件は緩和されたものの、「スキャナ保存」や「電子取引」の制度はまだまだ浸透しきれていません。
「領収書のスキャンってどの形式でいいの?」「PDFをメール添付で受け取ったらどう処理する?」といった細かいルールへの不安から、
“とりあえず印刷して保管”という運用が続いている企業も少なくありません。
⑤.紙の方が“安心”という心理的要因
人は変化に抵抗する生き物です。
「紙に印刷してファイルに閉じておけば確実」「いつでも見返せる」という安心感から、
「念のため印刷しておく」という行動が染みついている方も多いのではないでしょうか。
こうした心理的な要因は、制度や仕組みだけでは解決しきれず、組織文化の変化が求められるポイントです。
2.「紙が減らない」問題に対処する3つのステップ
STEP1:紙の発生源を“見える化”する
まずは、紙が発生している場所と理由を把握しましょう。
- ・誰がいつ、どの業務で紙を使っているのか
- ・なぜ印刷や原本提出が必要とされているのか
- ・電子データに置き換えられない理由は何か
こうした情報を洗い出すことで、紙を削減するためのボトルネックが明らかになります。
STEP2:紙が必要な“理由”に一つずつ対処する
紙文化には必ず“理由”があります。その理由を理解し、代替手段を一つずつ検討していくことが大切です。
たとえば・・・
- ・稟議・承認ルート → ワークフローの電子化と承認権限の整理
- ・原本保管ルール → 電子帳簿保存法の活用と社内ルールの改訂
- ・領収書原本の提出 → スキャナ保存制度の導入と業務フローの変更
経理だけでなく、総務や上長など関係部署と連携することで、現実的な改善が可能になります。
STEP3:小さな成功体験を積み上げる
一気に“紙ゼロ”を目指すのは現実的ではありません。
たとえば・・・
- 「交通費の申請だけは完全ペーパーレスにする」
- 「一部部門だけ試験的に原本不要にしてみる」
など、小さなステップから始めて成功事例を作っていくことが重要です。
「紙じゃなくても大丈夫だった」という実感が、周囲の不安を和らげ、次の改善につながっていきます。
3.まとめ
今回は紙が減らない理由についてでしたが、いかがでしたでしょうか。ペーパーレスを目指して導入したものの、紙が残ってしまうのはよくあります。また背景には、制度・ルール・習慣・心理的不安といった多様な要因がからんでいることもあります。
紙を減らすには、仕組みだけでなく「人の行動」や「社内文化」へのアプローチも重要です。
紙を削減することは、業務効率化や保管コスト削減だけでなく、
会社全体の透明性・柔軟性・デジタル推進力の向上にもつながります。
経費精算の現場において、「なぜ紙が必要なのか?」と立ち止まって考えることも大切です。 その問いかけが、社内の働き方を一歩前に進める原動力になります。
ちょっとした工夫やルールの理解で、グッとラクになります。
会社内だけでは細かい内容の改善が難しい・・・とお困りでしたら、一度弊社にお問い合わせいただければと思います。
貴社の「困った!」ことを詳しくお聞きし、業務改善のご提案等をさせて頂いております。
社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。
気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。→ 名古屋経理代行サポートセンター
今回紹介したシリーズが、皆さんの日々の業務の中で「助かった!」と思える小さなヒントになれば幸いです。
また次回のブログでお会いしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。